百年以上の歴史を持つ繁華街「南京東路」へ中国の民族楽器を探しに行こう!
こんにちは、上海ナビです! 少し前から日本でも人気沸騰中の「女子十二楽坊」、民族楽器で奏でられる伸びやかな演奏はナビも大好きです。彼女たちが使っているさまざまな中国の民族楽器、実物を見てみたいと思った方も多いはず。そんな皆さんに朗報です!実はここ上海に、中国民族楽器の老舗があるとのこと。お店の名前は「上海民族楽器一厰」、百年以上の歴史を持つ上海で一番古い繁華街「南京東路」にあります。それではさっそくお店に向かいましょう!
~南京東路を散策してみましょう!~
地下鉄2号線「南京東路」駅からスタート。南京東路を外灘へ向かって左側通行してください。この辺りは車の往来が激しいので気をつけて歩きましょう。
改装ラッシュのエリアを抜け、「河南中路」との交差点を渡ります。
「星火日夜」と「マクドナルド」の看板が華やかな「江西中路」との交差点。
この「星火日夜」、24時間営業のお店にぴったりな名前も気になり、夜に覗いてみましたが、本当に開いていました。上海名物のおやつが盛りだくさん。

石とパチンコ玉ではなく、正真正銘の飴です。舐めるより飾りたい?!
|

|

上海特産、空豆の乾物(ピリ辛味、ニンニク味、海苔味)。
|

立ち話に花が咲きます。
|

|
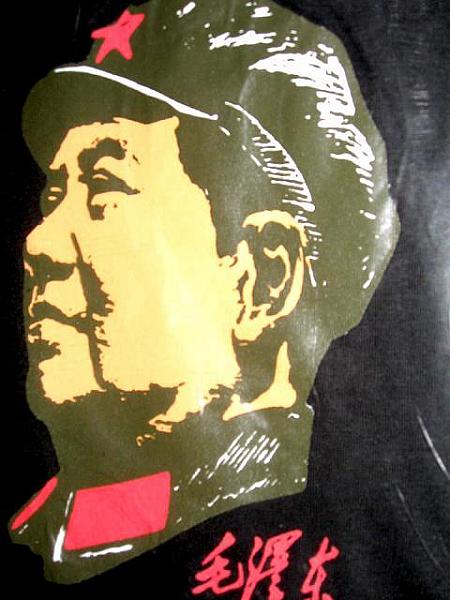
路地裏にも毛沢東Tシャツが。
|
綺麗に着飾ったマネキンの洋服はスカーフ・ストールを巻いたもの。チェーン展開する「上海故事」というこのお店では、スカーフ類や傘、バックなどを取り扱っています。日本ではあまり見かけない大胆なデザインの品物も入手可能。
店内にはたくさんの楽器がところ狭しと並べられています。「上海民族楽器一厰」といえば民族楽器を扱うお店の中でも老舗中の老舗。自社工場を持ち、職人の養成にも力を入れています。他にも、楽器貯蔵館や民族楽器に関する史料編纂なども手がけているそうですよ。
~民族楽器を手にとってみましょう~
本当にたくさんの種類がある中国民族楽器ですが、演奏方法によって大まかに分類することができるそうです。それでは、ちょっとドキドキしながら、お店にある楽器をご紹介していきましょう!
●弓で弾く弦楽器:二胡・高胡・申胡・京扳胡・革胡・馬頭琴・拉阮など
上から老紅木製(1627元)、黒檀製(1209元)、紅木製(554元)の二胡
「二胡」の胴に張りつけてあるのは蛇皮です。2本の金属弦を馬の尾で作られた弓で演奏します。
上
から竹製の京胡(240元)、紅木の上に塗料を塗った二胡(730元)、鉄梨木製の二胡(186元)
「京胡」は京劇の伴奏などに用いられる弦楽器で、高い音が特徴です。下の二つの二胡は塗料を塗って着色したもの。定番の赤の他に、緑や紫色のものもありましたよ。
二胡の個性は、胴に貼り付けられた蛇側の柄で決まるそうです。
こちらの二胡は「上海民族楽器一厰」オリジナルの新商品(3500元)!
二胡には蛇皮が使われているため、中国で購入して日本へ持ち込むためには特別な証明書の申請が必要になります。その証明書発行の手間を省くために考案されたのがこの水晶製の二胡。買ってすぐ持ち帰れますので旅行者には有難いですね。
●指で弾く弦楽器:古筝・琵琶・柳琴・古琴・阮・月琴・冬不拉・三弦・筝など
こちらは「古筝」。中国では琴(筝)の歴史は非常に古く、なんと「史記」にも古筝に関する記述が残るそうです。現在は一口に「こと」とまとめられてしまいますが、ルーツ・形・弦の本数・材料の違いなどにより、「きん(琴)」と「そう(箏)」に分けられるそうです。とっても奥が深い楽器なんですね。
牛の骨の象嵌が施された古筝(3017元)
ほかにも、牙・石・金・銅・漆などの細工がありました。デザインも豊富で、その奥深さはまさに熟練の職人技!ナビもお店で溜息をつきながらみとれてしまいました。
「双鶴朝陽」の古筝(1235元)
この「双鶴朝陽」という彫刻の図案は60年代から現在までずっと使われ続けています。上海民族楽器一厰のオリジナルで商標も取得しているそうです。
上:花梨木製琵琶(2006元)
下:白木製柳琴(287元)
茄子型の胴に4本または5本の弦を張った「琵琶」は日本でもお馴染み。琵琶の起源はペルシアで、中央アジア・中国・朝鮮半島を経て奈良時代に日本に伝来しました。始めは雅楽に用いられ(楽琵琶)、のちに盲僧琵琶・平家琵琶・薩摩(さつま)琵琶・筑前琵琶などが生まれたそうです。「柳琴」は琵琶によく似ていますが、一回り小振りで面板に孔があります。
左:ニレ製阮(599元)
中央:紅木雪梅月琴(1164元)
「阮」と「月琴」も形はよく似ていますが、共鳴箱の構造が違います。孔のあるほうが阮です。小さな丸い胴がかわいらしい月琴は、坂本龍馬が妻にプレゼントしたというエピソードでも有名です。
こちらは「三弦」(下)です。
日本の三味線に形が似ていますが、三味線は胴の両面に猫や犬の皮を張るのに対して、三弦は蛇の皮を張ります。また、三味線は銀杏の葉の形をした撥(ばち)で弾きますが、三弦は人差し指か義甲(付け爪のようなもの)で弾きます。
●管楽器:管・笛・巴烏(バウー)・簫(しょう)・哨吶(ソナー)・排簫・笙(しょう)・埙・葫芦絲(フルス)など
「哨吶」は日本で言うチャルメラ、にぎやかな音色が特色です。
上:石製の笛(1950元)
下:簫(950元)
「簫(しょう)」は中国版尺八、静かで哀愁ある音色が魅力です。読み方の同じ「笙(しょう)」は、鏡(かがみ)と呼ばれる頭(かしら)の上の部分の穴に竹の管が17本差し込んである楽器、少しややこしいですね。
「排簫(はいしょう)」は長さの異なる管を一列に並べて上端を吹く楽器で、西洋のパンパイプに当たります。
●打楽器:板琴・木琴・楊琴・沙槌・板・京鈸・戦鼓・京鑼・雲鑼など
堂鼓(白い太鼓)、腰鼓(赤い細長い太鼓)、戦鼓(小さい太鼓)
木魚
「堂鼓」は中国の武劇などで用いる太鼓で、日本の櫓太鼓(やぐらだいこ)に似たもの、4足の台上に上向きに据え2本のバチで打ちます。「腰鼓」は紐で首から掛け、腰のあたりに横につるして両手で打ち鳴らします。「戦鼓」は戦場で合図などに用いる太鼓です。銅鑼やシンバルの長く響く音の迫力はすごいんですよ。
こちらは
ミニチュアの楽器、小型ながら精巧な作りでなんだか豊かな気持ちになりますね。
いかがでしたか?楽器好きの方は必見のこのお店、ひょっとしたら日によって違う楽器に出会えるかもしれません。専門店ですから多少の無理も聞いていただける可能性あり、お店に置いていない楽器でも、工場や倉庫まで出向いて探せばきっと見つかるはずです。残念ながら日本語は通じませんが、楽器への情熱があれば、写真や絵、筆談での交渉もまた楽しいはず!お店はアットホームな雰囲気で、店員さんは皆とても親切です。皆さんもお気に入りの民族楽器を探してみてくださいね。以上、上海ナビでした。

